2026.02.05
「何かしたい」 その一歩が、難民の命を支える
公開日:
![]()
![]()
![]()
——創価学会平和委員会主催「難民映画上映会」を兵庫と東京で開催
1億2,000万人—
これは、2024年時点で、紛争や迫害によって家を追われた人々の数です。
過去12年間、増加の一途をたどり、日本の人口とほぼ同数に達しました。
日本に暮らす私たち一人ひとりにそれぞれの人生があるように、
1億2,000万という数字の向こうには、それぞれ異なるストーリーがあります。
突然の日常の崩壊、見知らぬ土地での不安、希望が失われそうな中で必死に生き抜くための決断——。
そうした状況に直面する人々が存在することを知り、思いをめぐらせる機会と、「自分には何ができるだろう」との思いに寄り添い、小さな行動のきっかけとなる場をつくりたい——。その願いのもと、創価学会平和委員会は、国連UNHCR協会が実施する「難民映画祭」の取り組みに賛同し、2017年から「難民映画自主上映会」を開催してきました。
スポーツを通して考える難民問題
2024年9月には、関西国際文化センター(兵庫県神戸市)で「難民映画祭パートナーズ」上映会を開催しました。上映作品は、スーダン内戦を生き延び2011年設立の新国家・南スーダンの一員となった青年グオル・マリアルさんが、祖国、また次世代のためにランナーとして走り続ける姿を描いた映画『戦火のランナー』でした。
この映画は、2021年には文部科学省選定作品にも選ばれ、また世界各地の映画祭でも賞を受賞しています。
上映後には、特定非営利活動法人「難民を助ける会(AAR Japan)」東京事務局兼関西担当で、ジャーナリストの中坪央暁氏に、南スーダンやウクライナ、またアジアにおける人道危機の現状についてご講演いただきました(事前収録)。
中坪氏は、なかでもロヒンギャ難民は、国際社会の関心が他地域に集中するなかで、忘れられている危機であるとした上で、彼らが直面している課題として、「難民キャンプの中では正規の教育は行われていません。またその後、職業に就くための職業訓練はありません。そもそもキャンプの中ではビジネスをすることは全面的に禁じられています。子どもたちには今現在何の未来もないという厳しい現実があります。」と訴えました。
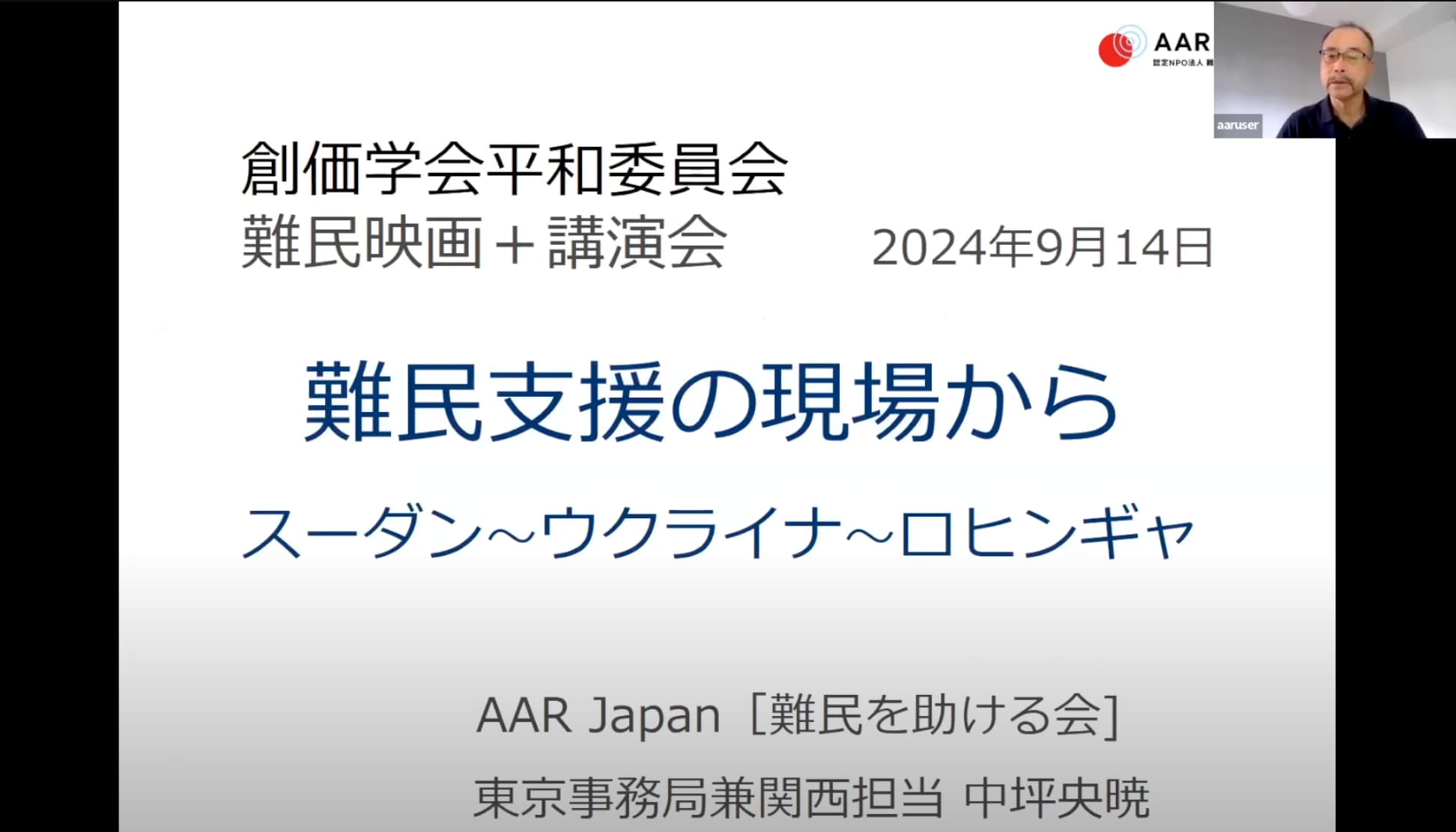
また会場では、国連UNHCR協会による「UNHCR難民アスリート写真展」を同時開催。
「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」に出場した難民選手団一人ひとりのストーリーや活躍を紹介する写真パネルの前では、多くの来場者が足を止め、真剣に鑑賞されていました。

当日は約120名の方にご参加いただき、参加者からは以下の声が寄せられました。
「あらゆる悲劇、言葉では言い表せない状況にたくさん面してきた中で、必死の思いで前に進む生命力と人間性の素晴らしさを感じました。」(20代)
「涙なくしては見られない映画でした。彼のようにそこまで祖国と呼べるこの国を思って行動ができるであろうか。誰もが、この地球民族の一員であることに心を置き、互いを思い合う行動を取れるよう、まずは我が家族、友人等を大切に思うことより活動したい。」(60代)
「多くの難民アスリートが出場したことを初めて知った。知ることにより関心が高まり難民問題にもさらに心が深まった。」(70代以上)
「あなたの普通は私たちの夢」ーパレスチナからのメッセージ
2025年4月には、難民映画自主上映会を「北とぴあ」(東京都北区)にて開催。
テーマは、パレスチナ自治区ガザ地区における人道危機で、ジャバリア難民キャンプ出身の産婦人科医、イゼルディン・アブラエーシュ博士がご家族を失ってもなお、憎しみではなく共存を訴える姿を描いたドキュメンタリー「私は憎まない」を上映しました。こちらも文部科学省選定作品であり、また世界各地で反響を呼んでいます。
上映終了後、日本国際ボランティアセンター(JVC)のパレスチナ事業現地代表である大澤みずほ氏から、オンラインでご講演いただきました。ガザ地区の人道危機の歴史的背景や現状についてお話があったほか、パレスチナの人々の「あなたたちが普通にできることは、私たちにとっての夢です」という言葉を紹介。また、彼らは「かわいそうな人たち」ではなく、緊急事態の中でも、コミュニティのためにお互いを支え、助け合う、力強い人々であることを忘れないでほしいと訴えました。

学生や若い世代の方々を含む約220名が参加し、以下の感想が寄せられました。
「今日を生きることが当たり前でない方々がたくさんいることを実感し、自分にできることはなにかを考えていきたいと思います。」(30代)
「宗教、思想、人種が違えど、生命は平等の当たり前なのに、なぜそうならないのか。娘を亡くしてもなお前に進む医師のように、私も諦めず何事か平和のために尽力していきたい。」(60代)
学びを、支援のためのアクションへつなぐ
今回紹介した2回の難民映画自主上映会では、会場にて、ご家庭で余っているハガキや切手などをご寄付いただける物品寄付コーナーを設置。
多くの方に真心のご協力をいただき、たくさんのハガキや切手、商品券、テレホンカードなどをご寄付いただき、それぞれAAR Japan、日本国際ボランティアセンターへお届けしました。


AAR Japanへの支援総額は4万7千円相当となりました。
映画から始まる連帯の輪——UNHCRプレッジとして登録
UNHCRは、4年に1度開催の「グローバル難民フォーラム」(次回は2027年)に向けて、”誰一人取り残さない”社会の実現を目指した難民支援の取り組みを「プレッジ(宣言)」として集めています。
創価学会による、上映会をはじめとした難民問題の意識啓発の取り組みも、正式なプレッジとして登録されています。
今後も、一人ひとりの学びと行動が難民支援につながるよう、取り組み続けてまいります。
この記事の取り組みは、以下の目標に寄与することを目指しています。
![]()
●目標1.貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。
![]()
●目標3.すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。
![]()
●目標4.質の高い教育をみんなに
すべての人に包摂的かつ公正の質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。
